はじめに
高齢化社会が進行する日本において、認知症の人が関与する刑事事件が社会的な関心を集めている。2022年時点で日本の65歳以上の高齢者のうち、認知症を有する人の割合は約7人に1人とされており、その数は今後も増加する見込みである。こうした中で、「認知症の人が犯罪を犯しても無罪になるのか」という問いは、法的・倫理的・社会的に非常に重要な問題である。
本稿では、日本の刑法における責任能力の概念を基礎として、認知症と刑事責任の関係を考察し、判例や法的枠組み、さらには犯罪予防や再発防止の観点を交えながら、認知症患者の刑事処遇のあり方を検討する。
責任能力と認知症:刑法の立場
日本の刑法においては、責任能力の有無が刑事責任を問う前提となっている。刑法第39条は次のように規定している。
刑法第39条第1項:「心神喪失者の行為は、罰しない」
刑法第39条第2項:「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」
ここでいう「心神喪失」とは、犯行時に自己の行為の善悪や違法性を判断する能力(是非弁別能力)および行動を制御する能力(行動制御能力)が完全に失われている状態を指す。対して、「心神耗弱」とは、これらの能力が著しく低下している状態である。
認知症は、記憶障害、見当識障害、判断力の低下、人格の変化などを特徴とする疾患であり、重度になると自己の行為を正しく理解し制御することが困難になる。そのため、認知症患者の刑事事件においては、犯行当時に「心神喪失」または「心神耗弱」に該当していたかどうかが、刑事責任の有無を判断する鍵となる。
裁判例から見る現実:無罪になるケースとならないケース
認知症の人が犯罪を犯した場合、すべてが無罪になるわけではない。以下に代表的な裁判例を紹介しつつ、具体的な判断の分岐点を検討する。
【事例1】認知症による心神喪失が認定され無罪となった例
2005年、認知症を患う高齢女性が、介護職員に暴行を加えて死亡させた事件において、裁判所は「被告人は当時、重度のアルツハイマー型認知症により、善悪の判断が全くできない状態にあった」と認定し、刑法第39条第1項を適用して無罪とした(地裁判決)。
この判決では、医師による精神鑑定が行われ、「被告人は犯行当時、行為の違法性を理解できなかった」とされたことが決め手となっている。
【事例2】心神耗弱とされて刑の減軽がなされた例
2017年のある殺人未遂事件では、被告人が軽度から中等度の認知症と診断されていた。裁判所は「被告人には限定的に是非弁別能力は残っていた」とし、完全な心神喪失には当たらないと判断。心神耗弱として、刑を減軽する判決を下した(地裁判決)。
【事例3】責任能力ありとして有罪となった例
2021年、認知症を有する高齢者が万引きを行った事例において、裁判所は「被告人は商品の価格や店のルールを理解しており、行為の違法性を認識していた」と判断し、責任能力が認められ有罪判決を下した。
このように、認知症であっても、その進行度や犯行当時の精神状態によっては、責任能力が認定され、有罪となるケースも多い。
認知症と責任能力の判断:エビデンスと実務
認知症と責任能力の関係を判断するにあたっては、精神鑑定が重要な役割を果たす。精神科医がDSM-5やICD-10などの診断基準に基づいて、患者の認知機能、記憶、判断力、行動抑制の程度を評価する。とくに以下の点が重視される。
-
MMSE(Mini Mental State Examination)などの認知機能テスト
-
行動観察(犯行前後の言動、生活歴)
-
MRIやSPECTなどの脳画像診断
-
介護記録・家族の証言 など
これらのデータをもとに、「犯行時に自己の行為の違法性を理解できたか」「行動をコントロールする能力があったか」が判断される。医学的な診断と法的判断は異なる次元であるため、医師の鑑定は絶対ではないが、裁判所にとって重要な指標である。
社会的課題と再発防止策
認知症患者による犯罪が社会問題化する中、単に無罪・有罪の議論に終始するのではなく、再発防止と社会的支援の充実が重要である。認知症患者が刑務所に収容されることは、医療・福祉の観点からも適切ではない場合が多い。
そのため、以下のような代替的措置が検討されている。
-
医療観察法の活用(心神喪失による重大事件における再発防止プログラム)
-
地域包括支援センターによる見守り体制
-
成年後見制度の利用
-
高齢者専門の司法処遇プログラム
厚生労働省の調査によれば、認知症高齢者の刑事事件は年々増加傾向にあり、特に「徘徊による窃盗」や「感情の爆発による暴行」などが典型例として報告されている。これらの背景には、家族の介護力の低下や社会的孤立がある。
おわりに
「認知症の人が犯罪を犯しても無罪になるのか」という問いに対して、答えは単純ではない。刑法上は、犯行時の精神状態に応じて責任能力の有無が個別に判断され、無罪になる場合もあれば有罪となることもある。
この判断には、法と医学の連携が不可欠であり、単に「認知症だから無罪」と決めつけることは誤りである。同時に、犯罪を未然に防ぐためには、地域社会全体での認知症患者への支援体制の構築が急務である。
参考文献
-
刑法(第39条)
-
厚生労働省「認知症施策の現状と課題」(2022)
-
日本精神神経学会「精神鑑定ガイドライン」
-
裁判例データベース(LEX/DB)
-
日本認知症学会「認知症と犯罪」報告書(2020)
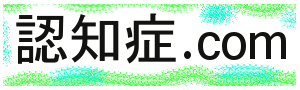
LEAVE A REPLY